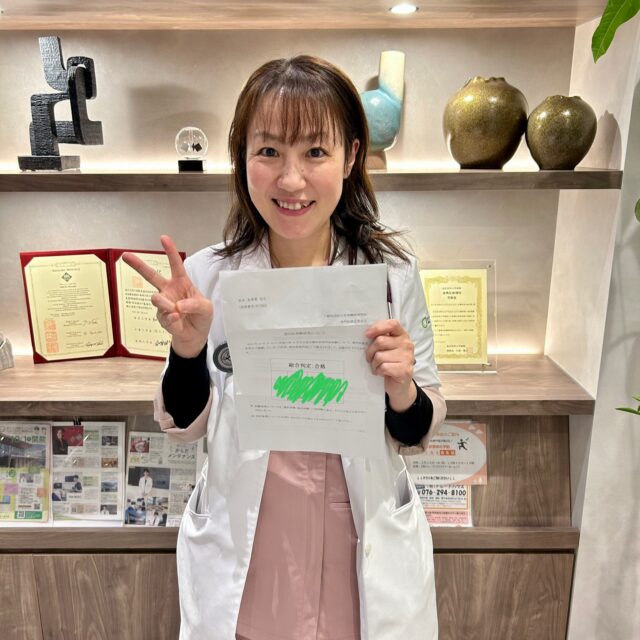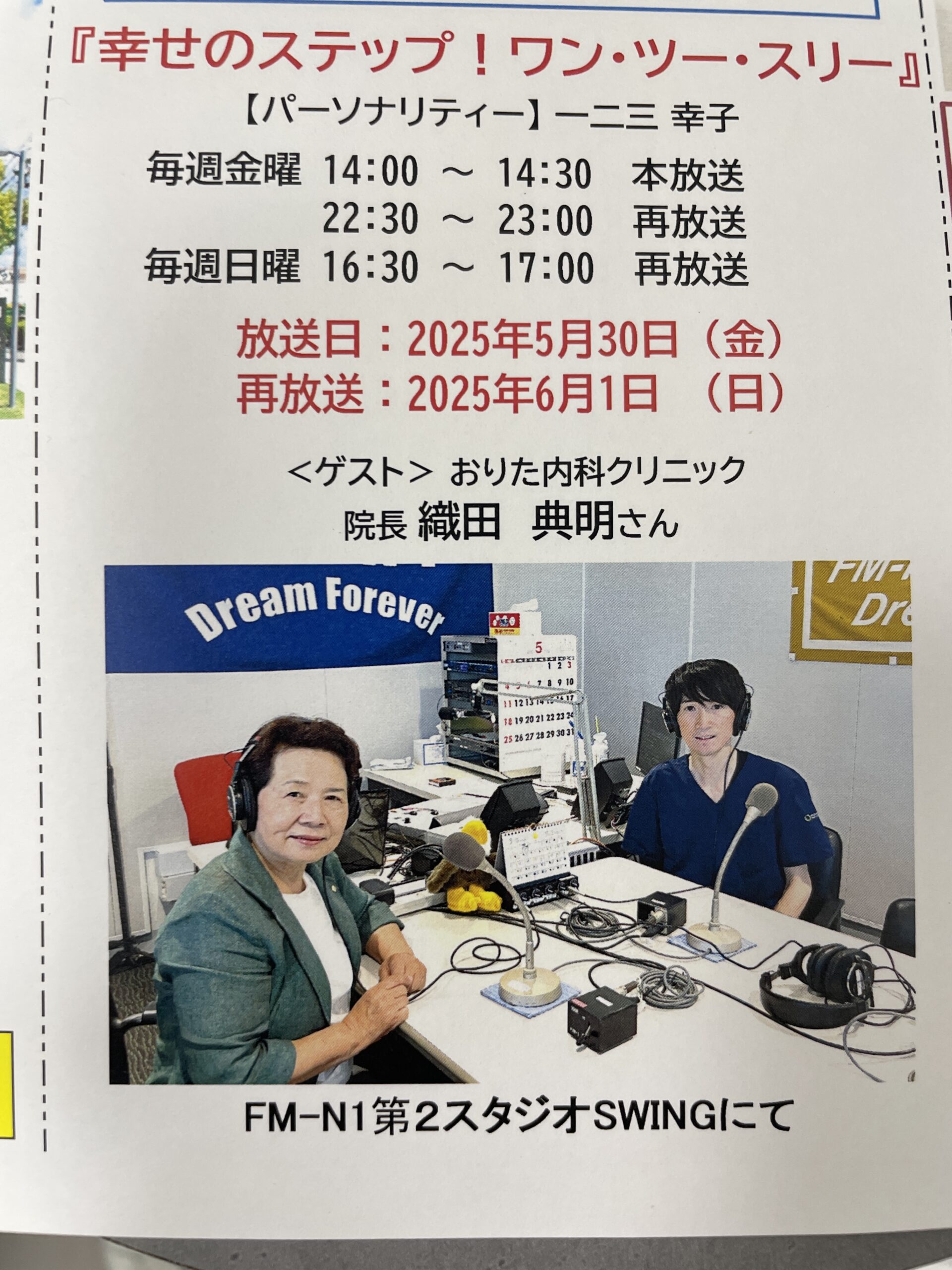こんにちは。おりた内科クリニック おなかとカメラと糖尿病 金沢院の院長 織田典明です。
私は、地域の皆様に寄り添い、消化器内科、糖尿病内科の外来診療はもちろん、在宅診療も行える「ライフパートナー」のような存在でありたいという思いから、10月1日に御経塚で内科クリニック開業を予定し準備をすすめています。さらに、地域の健康を支えるために、より身近な形で健康に関するお話や相談を行う場を設け、皆様の健康づくりのお手伝いをしていきたいと考え、地域の集まりに参加させていただき、お話しさせていただく地域活動を行っております。
今回は、
2024年8月31日に石川県野々市市の金沢南ケアハウスにて開催されました「認知症についての勉強会&座談会」に参加させていただき、
テーマ
みんなで学ぼう認知症~1人で悩まないで→地域のかかりつけ総合内科医としての役割
という内容で講演をさせていただきました。
認知症は誰にでも起こり得る病気であり、その支えには家族や地域の協力が欠かせません。
しかし、ご本人やご家族が「もしかして認知症ではないか」と悩みながらも、相談できずに一人で抱え込んでしまうケースが少なくないと感じております。
まずは地域の皆様一人ひとりが認知症を正しく理解し、早期発見や適切な対応につなげることが非常に重要だと思います。
認知症についての知識をつけることで偏見をなくし、医療や介護サービスの活用方法や予防の具体的な取り組みを知ることで、地域全体で患者さんやそのご家族を支える環境づくりの第一歩となります。
私たち『おりた内科クリニック おなかとカメラと糖尿病 金沢院』は、地域に寄り添うかかりつけ医として活動しています。日本内科学会総合内科専門医の私と、前職である金沢市立病院で認知症診療を実践してきた認知症サポート医である副院長が、「まず一歩を踏み出しやすい窓口となるクリニック」として、物忘れ相談に対応できる『物忘れ相談室外来』を設けています。
今回の講演会を主催してくださった金沢南ケアハウスのスタッフの皆様、そして野々市市郷・押野地区地域包括支援センターの皆様と密に連携を図りながら、「1人で悩まず、みんなで支える」地域づくりを目指していきます。私たちは、地域の皆様とともに、認知症に対する不安や悩みに寄り添い続けます。
このようなことが伝わってほしいという思いから下記の講演会を行いました。
地域の皆様に認知症の理解と地域で支え合う重要性についてお伝えできるようにお話ししました。

以下が発表スライドの概要です。
1. 認知症の基本情報
認知症とは?
認知症は、脳の細胞が死んでしまう、あるいは機能が低下することにより、記憶力や判断力が低下し、日常生活に支障をきたす病気です。一度正常に発達した脳の機能が後天的な原因で低下する点で、先天性の知的障害や正常な加齢による物忘れとは区別されます。
認知症と加齢による物忘れとの違い
| 項目 | 加齢による症状 | 認知症による症状 |
| 物忘れの範囲 | 体験の一部が思い出せない | 体験のすべてを忘れる |
| 自覚 | 物忘れの自覚がある | 物忘れの自覚がない |
| 日常生活 | 支障がない | 支障がある |
| 人格 | 変化がない | 変化することがある |
| 学習 | 新しいことを記憶できる | 新しいことを記憶できない |
| 妄想や幻覚 | 起こらない | 起こることがある |
加齢による物忘れでは、ヒントを与えられれば思い出せることが多く、日常生活に大きな支障をきたすことはありません。しかし、認知症ではヒントがあっても思い出せず、時間や場所の認識が難しくなるといった違いがあります。
最もわかりやすい具体例
・朝ごはんは食べたことは覚えているが、何を食べたは忘れてしまった→これは、朝ごはんを食べたという体験エピソードは覚えているが、その中の食事内容という一部分の詳細が思い出せない状態であり、加齢による物忘れのレベルです
・朝ごはんを食べた事自体を忘れてしまい、『朝ごはんはまだですか』と質問を繰り返す→これは、朝ごはんという体験エピソードを丸ごと忘れてしまっているため、認知症による病的な物忘れの可能性があります
主な原因と種類
認知症の主な種類は以下の通りです。それぞれに異なる原因と症状があるため、正確な診断が重要です。
・一番多いのはアルツハイマー型認知症
・65歳以上の7人に1人が認知症である
1.アルツハイマー型認知症(物忘れの代表的な疾患、ものとられ妄想が特徴的)
・原因: アミロイドβという異常なたんぱく質が脳細胞に沈着し、脳が萎縮する。
・特徴: 短期記憶をつかさどる海馬が初期に影響を受け、徐々に脳全体が萎縮。妄想(例: もの取られ妄想)も見られるが、人格は比較的保たれる。
2.脳血管性認知症(生活習慣病、動脈硬化が強く関わる認知症)
・原因: 脳卒中などで脳の血管が傷害され、脳細胞が酸素不足で死滅する。
・特徴: 高血圧や糖尿病などがリスク因子で、症状が階段状に悪化する(例: 突然悪化して一定の安定期が続く)。
3.レビー小体型認知症(小動物や虫、こびとなどの小さな生き物の幻視と動作のぎこちなさが特徴的)
・原因: レビー小体と呼ばれる異常なたんぱくが神経細胞に蓄積。
・特徴: 小動物や人影の幻視、筋肉の硬直や動作のぎこちなさ、パーキンソン病に似た症状が見られる。
4.前頭側頭型認知症(急激に進行する攻撃的な性格変化には注意)
・原因: 前頭葉や側頭葉の萎縮。
・特徴: 怒りっぽさ、人格の変化、反社会的行動(例: 万引き)や言語障害が特徴。
2. 治療可能な認知症とその重要性
認知症の中には、早期発見と適切な治療で改善が期待できるものもあります。そのため、物忘れが始まったときにはまずは以下のような疾患を除外することが重要となります。まずは、当クリニックへご相談ください。
1.甲状腺機能低下症
・特徴: 甲状腺ホルモンが不足することで、脳の働きも低下。首の腫れ、寒がり、むくみ、脱毛といった症状が伴います。
2.正常圧水頭症
・特徴: 脳脊髄液が脳を圧迫し、歩行障害、尿失禁、認知症症状がほぼ必発。頭部CTやMRIで診断可能。
3.慢性硬膜下血腫
・特徴: 頭部への衝撃後1~2か月経過してから、頭蓋内に血が溜まり症状が現れる。軽い頭部外傷でも注意が必要です。特に、抗血栓薬(血液をサラサラにするお薬)を飲んでいる方は危険性が高まります。頭部外傷後に出現した物忘れではまずはこの疾患を疑います。」
4.その他
・ビタミンや微量元素不足、睡眠薬の効きすぎなどの内服薬の副作用などが原因となることもあります。
★おかしいなと感じたら、まずは当院へお気軽にご相談ください。
3. 認知症の治療とケアの選択肢
薬物療法
認知症を根本的に治療する薬はまだありませんが、進行を遅らせる薬や落ち着かない、不安などの周辺症状を緩和する薬が調整します。
・抗認知症薬
ドネペジル(商品名:アリセプト)、ガランタミン(商品名:レミニール)、メマンチン(商品名:メマリー)、リバスチグミン(商品名:イクセロン、リバスタッチ)が代表的で、記憶力や認知機能の改善が期待されます。
・新薬レカネマブ(現在話題の新薬)
・特徴: 軽度アルツハイマー型認知症の原因物質アミロイドβを除去する効果がある。
・投与: 腰椎穿刺やアミロイドPETで診断後、2週間ごとに点滴を1年半続ける。
・副作用: 脳浮腫や脳出血のリスク(10%程度)。
現時点では、専門病院での投与が必要な状態です。
非薬物療法
認知症は現状では治すことが難しい病気であり、うまく付き合っていく方法を考えることが重要です。薬だけに頼らない予防対策がなによりも重要です。以下は具体例です。
1.運動療法→適度で続けられる運動が脳の活性化に重要です
・筋トレ(スロースクワット)と有酸素運動(速足ウォーキング)の組み合わせが推奨されます。週3回以上の運動が効果的です。
2.回想法→昔話を繰り返されることがありますが、ご本人様にとっては脳の活性化や安心感につながります
・昔の思い出を語ることで脳を活性化させ、孤独感や抑うつ感を和らげます。
☆ポイント
昔話ばかりして!と否定しないでください。過去への執着や現実逃避ではないことを周囲が理解して
本人のペースで話してもらうことが重要です。
3.リアリティオリエンテーション
・日常会話に正確な日時や場所を取り入れ、不安や混乱を軽減します。例えば、「今日は4/23で桜の満開宣言が出ました。もうすぐ3時ですね。今日のおやつは三色団子です。」と声をかけます。日付感覚や季節感を感じてもらうことで、脳が活性化し安心感を持つことができます。
☆ポイント
日常会話に正しい日時や場所を織り交ぜながら、散歩をしながら季節を感じてもらい、季節の花や食事のお話をすることは非常に効果的です。
注意:「今日は何月何日?」と問い詰めるのは逆効果です。
4.音楽療法・園芸療法→ご本人の趣味を大切にする
・昔好きだった曲を流したり、栽培した野菜を料理に活用したりして五感を刺激します。これにより、脳の活性化やリラックス効果が期待されます。
5.食事療法
・バランスの取れた和定食が理想的です。炭水化物や高タンパク・低脂肪食品を適度に摂取し、過度なアルコール摂取は控えしょう
4. 認知症予防のための実践例
脳はさまざまな場所でそれぞれ異なる働きを担っています。例えば、空間把握や人格、記憶、言語、聴覚、視覚、運動といった機能は、それぞれ特定の脳の部位と深く関係しています。このように、脳の異なる領域を意識的に使うことができる脳トレを行うことが、認知症予防において重要です。複数の脳の部位を同時に活用する活動を取り入れることで、脳全体の活性化を図ることができます。
スペシャル脳トレの具体例
体と頭を同時に使うトレーニングで、楽しみながら脳を活性化させます。
・クロスステップ: 足を交差しながら一定のリズムで移動します。
・クイズに挑戦: 漢字の色を答えるなど、認知と判断を同時に刺激する問題を解きます。
5. まとめ
講演のメッセージ
- 早期診断が鍵: おかしいと感じたらまずは当院へお気軽にご相談ください。
- 治療とケアの両立: 薬物療法だけでなく、日常生活に組み込める非薬物療法も活用しましょう。
- 地域で支え合う環境を作る: 医療と介護を活用し、本人や家族の負担を軽減することが大切です。
- 予防の意識を高める: 規則正しい生活、適切な運動、バランスの取れた食事を意識し、認知症予防に努めましょう。
★1人で悩まないず、物忘れにご不安がございましたら、まずは当院の『物忘れ相談室外来』へお気軽にご相談ください。
おりた内科クリニック おなかとカメラと糖尿病 金沢院
院長 織田 典明